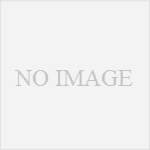推しが演じるあの役は、原作ではどんなふうに描かれてる? ドラマや映画の原作小説を紹介するこのコラム、今回は思いがけない視座から描かれるこのリーガルドラマだ!
■松山ケンイチ・主演! 「テミスの不確かな法廷」(NHK・2026)
原作は直島翔の同名小説『テミスの不確かな法廷』(角川文庫)。裁判官を主人公にしたリーガルミステリだ。今月6日に放送された第1回は、原作の第1話「カレンダーボーイ」が元になっている。
裁判官が主人公の作品といわれて思いつくのは、最近であれば朝の連続テレビ小説「虎に翼」(NHK)や、ドラマにもなった浅見理都の漫画『イチケイのカラス』(講談社)といったところだろうか。弁護士に比べるとと裁判官が主人公のリーガルものはあまり多くはない。そんな中、今回の「テミスの不確かな法廷」に続き、春には中山七里原作の『有罪、とAIは告げた』(小学館)もNHKでドラマ化されるとのことで、お、これは裁判官リーガルの波が来たか?
というわけで「テミスの不確かな法廷」である。特例判事補の安堂清春(松山ケンイチ)が単審(裁判官がひとりの裁判)で担当したのは、市長の乗ったタクシーと接触して当たり屋行為を働いた上、降りてきた市長に暴力を振るったとして、詐欺未遂と傷害で起訴された事件だ。だが古川検事(山崎樹範)の罪状読み上げに対し、被告の江沢卓郎(小林虎之介)は「全部違う」と否認。さらには弁護士は話を聞こうともしない、と批判した。
法廷での会話を聞いて安堂は弁護士の解任を宣告。だが市長の乗ったタクシーに接触したことと市長に暴力を振るったことは間違いないはず。いったい何が「全部違う」のか。安堂が江沢の自宅近辺を訪ね、近所の人に話を聞いていたとき、新たに江沢の弁護士に選任された小野崎乃亜(鳴海唯)と出会う。また、執行官の津村(市川実日子)が安堂にある情報をもたらし……。
人物設定や会話などに細かい違いはあるものの、事件とその真相は原作通りだ。法廷ミステリとして衝撃的かつ感動的などんでん返しもあり、自己紹介がわりの第1話として原作もドラマもとてもよくできている。だがこの小説/ドラマの肝はリーガルミステリの部分だけにあるのではない。安堂清春という主人公のパーソナリティこそが重要なのだ。
■ASD・ADHDの判事補視点で語られる物語の醍醐味
原作は直島翔の同名小説『テミスの不確かな法廷』(角川文庫)
主人公である裁判官・安堂は10歳のとき(ドラマでは13歳)に、他人の感情を推し量ることが苦手な自閉スペクトラム症(ASD)と衝動性がじっとしていることを許さない注意欠如多動症(ADHD)の診断を受けた。以来、主治医である山路先生(ドラマでは和久井映見)のカウンセリングを受けながら、社会の中で暮らしている。
裁判官としての知識や遂行能力にはなんら問題はない。ただ、公判中であっても急に落ち着かなくなり貧乏ゆすりがしたくなる、それを押さえるための刺戟として手を重い六法全書の下に敷いて圧迫を加えるといった描写から、同僚・上司とのコミュニケーションのズレの描写、あるいはケチャップ味のものしか受け付けないという症状など、作中では安堂の生活が実に細やかに描写される。何かに気を取られると他が疎かになり、たとえばジャージに革靴を履いて外出してしまうという例もそうだ。これらはすべてドラマでも再現されていた。
注目すべきは、原作ではそんな安堂の一人称で語られるという点にある。自分は宇宙人だ、地球人のことはよくわからない、けれど地球人に混じって生活していかなくてはならない……その苦労と苦悩が本人の言葉で綴られるのだ。中でも、ドラマではカットされていたが、原作に特に印象深いくだりがあった。
山路が安堂に「ひと月ぶりだね」と挨拶する。ここで安堂は「山路のあいさつの一言一句を反芻し、それがひっかけ問題であることに気づいた」とある。安堂は反射的に「ひと月ぶりではなくて、ひと月と三日ぶりです」と訂正しそうになり、踏みとどまる。脳の衝動のままにそう返すのは場にそぐわないと気づき、一呼吸おいて、「先生、お久しぶりです」という返事を口にするのだ。「知力で脳を制御せよというのが、山路が出会いの日から、長く安堂に言い聞かせてきたことであった」
この場面には蒙を開かれた思いがした。最近は「生きづらさ」という言葉がインフレを起こしている気がして、創作物の紹介にこの言葉が使われるのに辟易していたのだが、確かにすべての応答に対して逐一「正解を探す」という対応をしていると思うと、それはもう「生きづらさ」と言うしかないじゃないか。彼らの何がたいへんなのか、これはその一端とはいえ、実にきれいにストンと腑に落ちたのだ。
もちろんASDやADHDにもグラデーションがあり、知力で脳を制御するというのは誰もができることではない。けれど安堂には司法試験に通るだけの知力があった。本書では自らの持つあらゆる衝動に、安堂がどう向き合い、どう対処するかが本人の視点でつぶさに描かれる。その自制の努力の描写は圧巻だ。なお、私も言っちゃいけないことをぽろっと口に出して後悔することがよくあるので、喋る前に知力(あるのか? )で脳を制御せねばと心に刻んだ次第である。
■始まったばかりのドラマ、今後はここに注目!
だがドラマでは、安堂の心の声をすべてセリフやモノローグにするわけにはいかない。そこで松山ケンイチさんの演技ですよ。いやすごいな! 原作で読んだ安堂そのものだ。「ここ原作とイメージ違うな」という部分が1ミリもないよ。これ「虎に翼」でチョー厳格な判事・桂場等一郎を演じたのとホントに同じ人なのか? 作中で描かれる安堂の動きがそのまま画面に登場し、「なるほどこういうことか」と膝を打ったのも一度や二度ではない。原作を読んだ人はぜひドラマを、ドラマを見た人はぜひ原作を読んでほしい。どちらが先でも「こういうことか」と思えるはずだ。
ドラマのもうひとつの見どころは、他者の反応が俯瞰して見られること。原作は他人の感情を推し量ることが苦手な安堂の視点なので、周囲の人の言動は「見たまま」しか描かれない。まあ、それでもなんとなく見当がつくように書かれているのが小説の上手さなのだが、ドラマではそれをはっきりと見せてくれる。
たとえば同僚は安堂のことをどう思っているか。書記官はどう思っているか。ドラマで、安藤はある写真について自分の判断に自信がないからと書記官に見せる場面がある(これは原作にはない場面)が、そこで書記官が戸惑う様子に安堂はまるで気づいていない。ドラマでは原作以上に、安堂が周囲から変な人と思われている様子が伝わってくる。
「あれ?」と思ったのは、安堂が弁護士を解任したことを同僚の落合判事補(恒松祐里・原作では男性)が批判する場面だ。しかし原作の落合はむしろ安堂の決断を讃えている。この改変は何だろう? もしかして、周囲がこれから少しずつ安堂を理解していく様子を描くため、わざとマイナスからスタートさせたのではないだろうか。この想像が正しければ、きっと原作にはない周囲の人々の反応も描かれていくに違いない。
細かい改変はいろいろあった。落合判事補だけでなく執行官の津村も原作では男性だったし、古川検事のキャラも変わっている。また、原作の舞台はY市(さまざまな描写から山口だと思われる)だが、ドラマでは群馬県に変更されていた。しかも第2話は改変どころか原作にはないドラマオリジナル回だ。
ということは、今後も原作にはない展開が用意されているのかも。ただ、第1話のラストで、何やら思わせぶりに登場した「再審」という言葉──これは先月刊行された続編『テミスの不確かな法廷 再審の証人』のことではないかしら。ネタバレを気にしない人は続編もチェックだ。しかも再審について意味ありげに話していた結城次長検事を演じるのは小木茂光さんである。腹に一物ある慇懃な役をやらせたら天下一品の小木さんである。これはもうワクワクしかない! 連作仕立ての原作にオリジナル要素を混ぜつつ、どう一編のドラマにしていくのか──これからが楽しみだぞ。
大矢博子
書評家。著書に『クリスティを読む! ミステリの女王の名作入門講座』(東京創元社)、『歴史・時代小説 縦横無尽の読みくらべガイド』(文春文庫)、『読み出したらとまらない! 女子ミステリーマストリード100』(日経文芸文庫)など。名古屋を拠点にラジオでのブックナビゲーターや読書会主催などの活動もしている。
———
Source: uenon.jp